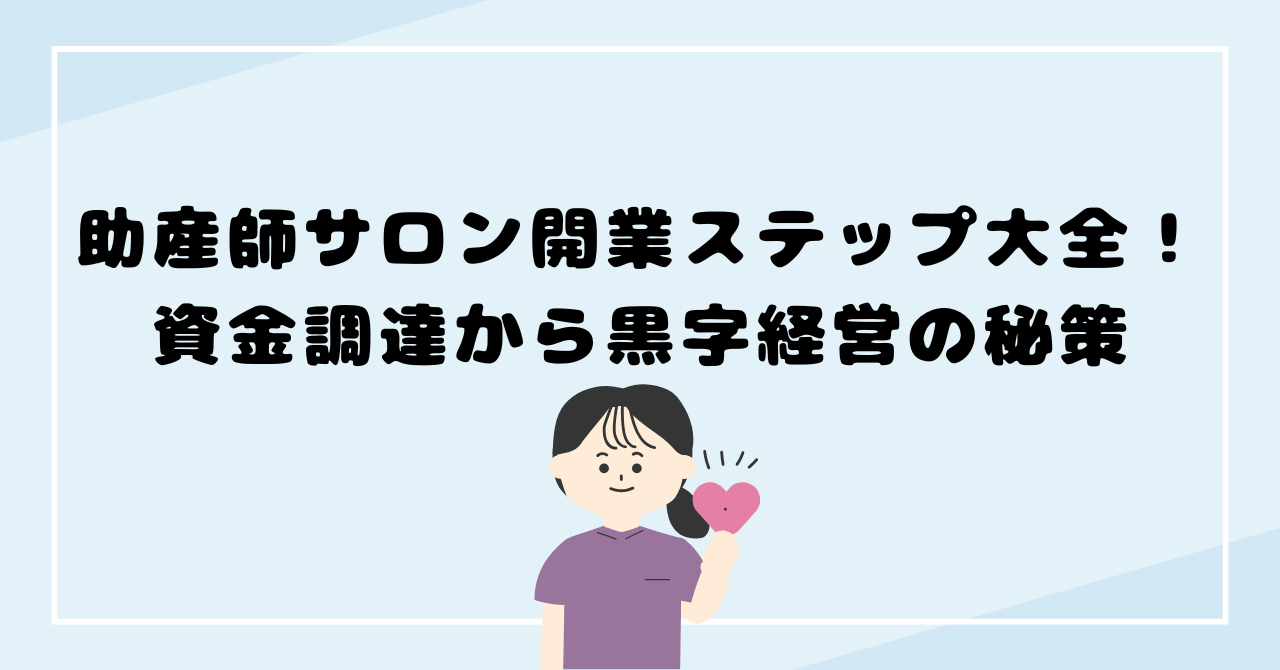「助産師としての経験を活かして、もっと自分らしい形で母子をサポートしたい」「いつかは自分のサロンを開業したいけれど、何から手をつけていいかわからない」
そのように考えている助産師の方は、決して少なくありません。病院やクリニックでの勤務とは異なり、自身の理念に基づいたケアを、時間をかけてじっくり提供できるのが「助産師 サロン開業」の大きな魅力です。
しかし、開業には夢だけでなく、事業計画、資金調達、法的手続き、そして経営という現実的な課題が伴います。本記事では、助産師サロン開業という夢に向かうあなたのために、その具体的なステップを一つひとつ丁寧に解説します。資金調達のノウハウから、黒字経営を続けるための秘策まで、成功への道を網羅した完全ガイドです。

なぜ今、助産師のサロン開業が求められているのか?
近年、産後ケアの需要は急速に高まっています。核家族化が進み、地域とのつながりが希薄になる中で、産後の母親が孤立し、心身の不調を抱えてしまうケースが増えているからです。そんな中、専門的な知識と経験を持つ助産師が、地域に根ざして提供するきめ細やかなサポートは、多くの母親にとってまさに「駆け込み寺」のような存在となり得ます。
助産師がサロンを開業することは、自分らしい働き方を実現するだけでなく、地域社会の母子保健に大きく貢献する、非常に価値のある選択なのです。
助産師サロン開業|7つの必須ステップ
それでは、具体的に助産師がサロンを開業するためのステップを見ていきましょう。やるべきことは多岐にわたりますが、一つずつ着実にクリアしていくことが成功への鍵です。
ステップ1:コンセプト設計と事業計画の策定
全ての土台となるのが、コンセプトと事業計画です。これが曖昧なままだと、後のステップで必ずつまずいてしまいます。
- 誰に(ターゲット)
どんなことで悩んでいる、どんな母親と赤ちゃんを一番サポートしたいですか?(例:初めての育児に不安を抱える初産婦、母乳育児がうまくいかない母親など) - 何を(サービス)
ターゲットの悩みを解決するために、どんなサービスを提供しますか?(例:母乳外来、育児相談、産後ケア、ベビーマッサージ教室など) - どのように(提供方法)
出張専門、自宅サロン、テナントなど、どのような形態でサービスを提供しますか? - なぜ(理念・強み)
他のサロンや病院ではなく、「あなたのサロン」が選ばれる理由は何ですか?あなた自身の経験や価値観を言語化し、サロンの「軸」を作りましょう。
これらの要素を固めたら、具体的な数値目標を盛り込んだ「事業計画書」を作成します。事業計画書は、後述する資金調達の際にも不可欠な書類です。
事業計画についての詳しい記事はこちらから👇
ステップ2:開業形態を決め、法的手続きを進める
助産師のサロン開業は、提供するサービス内容によって必要な手続きが異なります。特に「分娩(助産介助)を扱うかどうか」が大きな分岐点です。
- 分娩を扱う「助産所」として開業する場合
医療法に基づき、開設後10日以内に管轄の保健所へ「助産所開設届」の提出が必要です。また、分娩を扱う場合は、緊急時に連携する嘱託医師や嘱託医療機関を確保しなければなりません。建物の構造設備にも基準があるため、計画段階で保健所に相談することが不可欠です。 - 分娩を扱わない「サロン」として開業する場合
母乳相談や産後ケアのみを行う場合は、分娩を扱う助産所のような厳しい設備基準や嘱託医師の確保は必須ではありません。この形態は、助産師が持つ知識や経験を活かしながら、より手軽に始められるのがメリットです。個人事業主として「開業届」を税務署に提出することから始めます。
多くの場合、まずは分娩を扱わないサロン形式からスタートし、将来的に助産所へとステップアップしていくのが現実的でしょう。どちらの形態を選ぶにせよ、お住まいの自治体の保健所や税務署に事前に相談することが重要です。

ステップ3:最重要課題!資金調達を成功させる
助産師のサロン開業で最も頭を悩ませるのが資金の問題です。自己資金だけで全てを賄うのが理想ですが、多くの場合、融資の活用を検討することになります。
開業資金の内訳
開業に必要な資金は「初期投資(設備資金)」と「運転資金」の2つに分けられます。
- 初期投資
物件取得費(敷金・礼金)、内装工事費、什器・備品購入費、広告宣伝費など。 - 運転資金
家賃、水道光熱費、通信費、消耗品費、自身の生活費など。軌道に乗るまでの間の運転資金として、最低でも6ヶ月分は用意しておくと安心です。
主な資金調達方法
- 日本政策金融公庫「新創業融資制度」
政府系金融機関で、これから事業を始める人にとって最も頼りになる相談先です。 - 自治体の制度融資
都道府県や市区町村が提供している融資制度で、金利が低めに設定されていることが多いのが特徴です。 - 補助金・助成金
国や自治体が提供する、返済不要の資金です。「小規模事業者持続化補助金」や女性起業家支援の制度など、活用できるものがないか必ずリサーチしましょう。
融資の審査では、ステップ1で作成した事業計画書の説得力が鍵を握ります。情熱と具体性のある計画書を準備しましょう。
融資についての詳しい記事はこちらから👇

ステップ4:物件選びとリラックスできる空間づくり
助産師のサロン開業の場所と空間は、お客様の満足度に直結する重要な要素です。
- 立地選び
ターゲット顧客層が多く住むエリアを選びましょう。駅からのアクセスや駐車場の有無なども考慮します。 - 自宅 or テナント
自宅開業は家賃を抑えられますが、生活感が出やすい側面も。テナントは固定費がかかりますが、サロンのコンセプトを表現しやすいです。メリット・デメリットを比較検討しましょう。 - 空間づくり
母親と赤ちゃんが心からリラックスできる空間を目指しましょう。清潔感はもちろん、温かみのある照明や落ち着いた色調の内装、心地よい香りなど、五感に働きかける工夫が大切です。プライバシーに配慮した授乳やおむつ替えのスペースは必須です。
ステップ5:集客の仕組みを構築する
どんなに素晴らしいサロンを作っても、お客様に来てもらえなければ経営は成り立ちません。開業準備と並行して、集客の準備も進めましょう。
オンライン集客
- ウェブサイト・ブログ
サロンの公式な「顔」です。サービス内容、料金、想いなどを詳しく伝えましょう。ブログで専門知識を発信することは、信頼獲得とSEO対策に繋がります。 - SNSの活用
Instagramはサロンの雰囲気や人柄を伝えやすく、ターゲット層の利用率も高いため、非常に有効です。LINE公式アカウントを予約や相談の窓口にするのもおすすめです。
オフライン集客
- 地域連携
地域の産婦人科や小児科、子育て支援センターなどに挨拶に行き、パンフレットを置いてもらうなど連携をお願いしてみましょう。 - 口コミ
最も強力な集客ツールは、満足したお客様からの「口コミ」です。期待以上のサービスを提供することが全ての基本です。
おすすめの予約&業務予約管理システムはこちらから👇

ステップ6:黒字経営を続けるための運営戦略
開業はゴールではなく、スタートです。サロンを長く継続させていくためには、経営者としての視点が欠かせません。
- リピーターの育成
安定した経営のためには、一度来てくれたお客様に「また来たい」と思ってもらうことが何よりも重要です。丁寧なアフターフォローや、一人ひとりに合わせた提案を心がけましょう。 - 顧客管理
お客様の情報(利用履歴、相談内容など)をきちんと管理し、次回のサービス提供に活かしましょう。 - 客単価アップの工夫
単発のサービスだけでなく、複数回セットのコースメニューを作ったり、おすすめのケア用品を販売したりすることで、客単価の向上が見込めます。 - 適切な価格設定
安売りはせず、自身の技術や提供価値に見合った価格を設定しましょう。
ステップ7:賠償責任保険への加入と継続的な学習
万が一の事態に備え、助産師賠償責任保険への加入は必須です。安心してサービスを提供するためにも、必ず手続きを済ませましょう。日本助産師会などで加入できます。
また、医療やケアの世界は日進月歩です。常に最新の知識や技術を学び続ける姿勢が、お客様からの信頼に繋がります。研修会やセミナーにも積極的に参加し、常にスキルをアップデートしていきましょう。
日本助産師会のHPはこちらから👇

まとめ:一歩踏み出し、あなたの理想のサロンを実現しよう
助産師のサロン開業は、決して簡単な道のりではありません。
しかし、しっかりとした準備と計画があれば、その夢は必ず実現できます。本記事で紹介した7つのステップを参考に、まずは「コンセプト設計」から始めてみてください。
あなたの専門性と温かい心遣いを待っている母親と赤ちゃんが、あなたの地域にはたくさんいるはずです。
「助産師としてサロンを開業する」というあなたの決断が、多くの家族を笑顔にし、あなた自身のキャリアをさらに輝かせる大きな一歩となることを、心から応援しています。